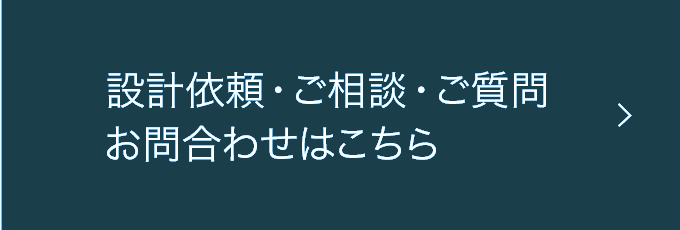住宅の照明の考え方
2020年3月も半ば、今年は特殊な社会事情から、仕事で街中を行き来してもいつもよりも静かなビル間ですね。
なかなか集まったり出かけたりという事はし辛いですが、いよいよ春の訪れ、四季の中でも雪がみぞれ、そして雨に変わり、少しずつ土が現れ、木々が芽吹きという生命が息を吹き返すような春の気配をちょっとした散歩にも着々と感じられるのは良いものです。
富谷洋介建築設計では、現在お打ち合わせの際、欠礼となりますがマスク着用、前後の手指消毒、換気の徹底などのをさせて頂きながら、通常通り業務をさせていただいております。※ご要望、必要に応じましてPCでのビデオ会議等、対面以外でのお打ち合わせも活用が可能です。
設計の大半は頭の中で進みます、少し先の未来のため、引き続き楽しく、豊かな建築空間の設計を進めて行きましょう。
今日は自宅での時間に撮った写真で照明の話を少し。
旧来、シーリングライトを部屋の中央に配置し、部屋全体を均一に照らすということが多かった照明ですが、 計画の際にはご説明をさせて戴くのですが、 明るくするばかりが良いことではなく、照明にも場所ごとに適切な手法があり、よりその場所ごとに効果を与える方法を採用して計画を行うことが大切となります。
基本的に「明るくあるべき場所」(家事や本を読んだりといった、機能的に明るさが必要な場所)に必要な明るさがあり、全体空間の雰囲気として「心地よい明るさであるべき場所」(壁・床・天井といった、空間自体の明るさと感じる場所)をどう照らすのが合理的で快適かということを考えることになります。 (タスク・アンビエント照明)
それぞれお好みや、子供部屋などシーリング照明で全体を明るくすることが良い室もありますが、ダイニングはテーブル面が、キッチンではシンク天板が、など、必要とするところが明るければ、後者の空間の明るさは少し抑え目の方が落ち着いた、快適な光の状態になる場合が多いです。
例としては、
↓これは部屋の中心付近のダウンライトを点灯しています(ソファ・テーブル近辺で)文字を読むための明るさ。

↓それに対してこちらは、壁際のスポットライトを点灯しています。ウォールウォッシャーと言って、壁面を照らし空間の明るさ・広さ感を出すことができます。同じ照明の数でも、どこを照らすかで随分と空間の印象が変わります。

↓ちなみにこちらはテレビ裏の壁を照らす間接照明。柔らかい光で空間を照らすことができます。

↓全部点けるとこのような感じ、実際の生活ではこういう状態が必要なことはほぼ無いですね。ゆったりと過ごすだけであればスポットライトか間接照明の組み合わせで十分です。

↓その他、器具自体も目に見える位置に配置し、そこから拡散する光を出すブラケット照明であったり、

↓ダイニングや吹き抜けなどで机上面の明るさをとったり、器具のデザインを見せたりするペンダント照明など、さまざまな照明を組み合わせて、より空間が求める機能、快適性に合った照明器具・手法を選択し、ご提案していきます。

↓以下は関係ないですがちょうどあった模型にも照明が当たっていたので。見せたい面にしっかりと光が当たると、物も活きてきますね。


話は全く変わりますが…昨年竣工の「Cafe Ebru」(カフェエブル)さんからご依頼いただき、追加の小さなサインを設置させていただきました。
オープン後の周辺の人通りの印象から、逆側からの視認性を高めたいとのこと。壁面に張り付けるのではなく、歩行者からも好ましく見やすい位置の突き出しサインとしてみました。可愛らしくよい感じです。製作はサイン、表札などいつもお世話になっているモダンワーク様でお願いしました。